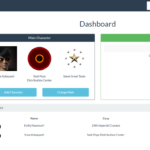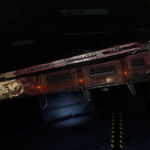https://www.eveonline.com/news/view/equinox-mining-balance-philosophy-and-learnings
経済システムのバランス調整は、現実世界においてもゲームの仮想世界においても常に難しい問題ですが、先日の採掘バランスの調整に関するCCPの開発者ブログではそのリアル経済とゲーム経済の考え方の違いに触れていたので、今回はその経済学的な視点に注目しつつ、ゲーム経済のバランス調整の難しさについて記事を書いてみたいと思います。
根本的な問題:リアルすぎる経済は「本末転倒」
リアル経済政策の目的
現実の経済政策は、基本的に「人類全体の幸福と社会の繁栄」を目指して設計されます。具体的には以下のような目標が設定されます:
- 経済成長の促進と持続可能性の確保
- 雇用の創出と所得の公平な分配
- インフレーションや為替相場の安定化
- 社会保障制度の維持と財政の健全性
これらは地域や国家といった単位で相互に矛盾することもある複雑な目標であり、「最適解」が常に存在するわけではなく、しばしば社会的合意と政治的判断に委ねられます。
ゲーム経済政策の目的
一方、EVE Onlineのような仮想世界における経済政策の最終目的は一言でいえば「プレイヤーの楽しさの最大化」です。CCP Okamiが述べているように:
「実際のところ、New Edenはより楽しさが減少していると多くのプレイヤーが感じています。以前アクセスできていた多くの『おもちゃ』へのアクセスが減少し、より効率が良くない結果をもたらす新しい効率パズルを事実上導入しました。」
つまり単純な話、リアルだと生きるためにつまらないこともしなくてはならないですが、ゲームでも全く同じな世界線を突きつけられたらそりゃ楽しくないのは容易に想像できるわけです。
人々がゲームをやる一番の理由は「現実からの逃避」というのは多く語られている話ですが、まずそこをしっかりと認識しないといけないと言っているあたり、皮肉なのか素で言っているのかわからないですが、いかにもEVEOnlineの開発者らしいなと思います。
社会的価値と経済的価値の扱い
リアル経済における社会的価値
現実経済では、純粋な経済効率とは別に社会的価値が重視されます:
- 社会的公正と機会均等:格差是正や社会的弱者への配慮
- 持続可能性と環境配慮:短期的経済成長と長期的持続可能性のバランス
- 文化的・歴史的価値の保全:経済合理性だけでは測れない価値の尊重
これらの価値観は、純粋な経済効率とはしばしば相反し、社会的合意形成が求められます。
ゲーム経済における多様なプレイスタイルの共存
EVE Onlineでは、異なるプレイスタイルの共存が重要な課題となります:
- ソロプレイヤーvs組織プレイヤー
CCP Okamiは「個人採掘vs集団採掘vs複数アカウント採掘」のバランスに言及 - カジュアルvsハードコア
プレイ時間や投資度合いの異なるプレイヤー層の共存 - 多様なゲームプレイの価値
「効率」だけでなく「探索」や「リスク」など多様な楽しみ方の尊重
結論として、ゲーム内で「効率的な経済」を追求することが、必ずしも「楽しいゲーム」をもたらすとは限らないということです。CCP Okamiはこの矛盾を以下のように表現しています:
「デザインでは、EVEの中核的なシミュレーションエンジンを保護するか、それとも宇宙で解決できる可能性のある課題やゲームプレイを排除してそのエンジンに影響を与えるかを常に注意深く考える必要があります。しかし、時には物事をより楽しくするためにリバランスする必要もあります。」
経済指標から見るEquinoxの影響
鉱物価格指数(MPI)の急上昇
Equinox拡張後、鉱物価格指数(Mineral Price Index)が急激に上昇しました。MPIの上昇は、市場における鉱物の供給不足を示唆しているわけですが、これはEquinox調整によって採掘に構造的な問題が生じていることを示していました。
投資収益率(ROI)の不均衡
Equinox拡張における一つの重要な問題として、異なる活動間のROI(Return On Investment:投資利益率)の不均衡と言っています。注目すべきは以下の点:
- 採掘 vs ラッティングのROI格差
Nullsecにおいて採掘活動よりラッティングの方が時間当たりの収益(ISK/hour)が高くなった結果、採掘活動から離れる傾向が強まった - Metenoxの費用対効果
新たに導入されたMetenox月面採掘機は、特に低~中程度の月における高いROIをもたらしたが、通常の鉱石を抽出できないという制限により、パイライトなどの特定鉱物の供給減少を引き起こし、市場バランスを崩す要因となった
コストバランスの難しさ
投入・産出比率のリバランス
開発者CCP OkamiはEquinoxでの採掘調整を以下のように例えています:
以前のサイトでは100ISK相当の価値が大きな20ISK紙幣5枚で配置されていた。Equinoxでは理論上200ISK相当の価値が提供されたが、それが5ISK札と1ISK札の形で広範囲に散らばっていた。これにより潜在的な総価値は上昇したが、全てを回収するための労働投入量(労働コスト)が大幅に増加した。
つまり、量は増やしたが効率を悪くした結果、そのコスト高が思ったより市場に反映されたということです。
- 採掘の実質的な時間当たり収益(実効ISK/hour)の低下
- 労働集約度の高い活動へのシフトによる市場供給量の減少
- 供給減少による鉱物価格の上昇(MPI高騰)
ストックパイル(備蓄)に対する市場反応の難しさ
鉱物経済における調整の難しさの一つは、最近国内でも問題となっている備蓄米と似たような問題です。データでみるとどうやら多くのプレイヤーやコーポは大量の鉱石やミネラルを備蓄しているらしく、開発者が指摘するように新旧の鉱石・鉱物を技術的に区別することは困難であるため、例えば精錬率のような単純な調整パラメータを変更すると、備蓄資源の価値も同時に変化するので、意図した供給増加を超えた市場の過剰反応を引き起こす可能性があると言っています。
これは経済学的には「予期せぬ資産効果」と呼べるもので、このような市場の複雑性も調整が難しい理由の一つとなっているようです。
「多くのプレイヤーは鉱石を保管しています。残念ながら、バランス変更の前後で鉱石やミネラルを技術的にクリーンに分離する方法はありません。これは、精錬率のような小さな変更でさえ、私たちが解決しようとしている問題に対して巨大な反対の影響を与える可能性があることを意味します。」
結局のところ、仮想世界における経済施策もリアルと同じく「人間の行動と期待をどう理解し、予測するか」という根本的な課題にあります。データを見ながら効果を測定し、少しづつ継続的な調整を続けることが「楽しい経済」を維持する鍵だということなのではないでしょうか。
ちなみにEquinoxのもう一つの大きな失敗は領有(Sov)に関する調整です。WorkForceの導入はおそらく領土運営のコストを増大させることで大手コアリションの領土を縮小させることを意図していたと思いますが、結果は真逆でかえって大手コアリションは大量の構成員の経済的欲求を満足させるために、領土をさらに拡大する方向に動きました(端的な例が南東部の我々SGGRNに降りかかったこと)。そして単に領土運営がめんどくさくなっただけであり、Nullが全体的に停滞する要因になったように見えます。
CCPはおそらくこれも認識していると思いますが、どのような対応するかはこの鉱石価格の調整以降になるでしょう。
Share this content: